
- やっぱり荷物が結構邪魔になる。輪行袋、履き替え用の折り畳み靴、スマートフォンの充電用バッテリ。基本的にこの3つが重さの源なんだけど、靴はビンディングで電車乗り継ぐ覚悟決めれば靴は抜けるなあとか。
- 膝が冷える。最後の4時間目の途中、膝が痛くて回せなかった。登りは問題なかったので、風のせい?長距離走る際は膝が隠れているレーパンがベストかも。
- 日焼けで痛い。日焼け止めの塗り直しが必要。
- 食べる時間が必要。これをカットするためには予め補給食を(エナジー系以外に)持ってないと。

中身を見てからでないと絶対買えない本、そのひとつは参考書。

地図情報の活用方法を少し勉強したいなと思い、ウェブで見れる情報を少しずつ読んでいたのですが、そろそろまとまった知識として学びたいと思い、参考書籍を購入することに。重いし高いし、amazonで書評頼りに購入しようかと思ったのですが、この手の参考書籍は情報量とその見せ方の合う/合わないが個人差の大きいものなので、やっぱり中身を見てからにしようとジュンク堂へ。
amazonのなか見!検索は、物語とか雑誌とかはいいんですけど、参考書はなんというか使うときの「サイズ感」も大事なので、なか見!検索でディスプレイで見ても使い勝手がわからないんですよね。
という訳でジュンク堂でコンピュータの棚をうろうろしたんですが、意外と地図アプリに的を絞った開発書というのはないんですね。欲しい内容とは異なるんだけど『mapion・日本一の地図システムの作り方』が非常に興味をそそられる、参考になりそうな本だったんですがなんとか思いとどまり、GPS情報の詳細かGoogle Mapsの詳細かに的を絞って選んだのが『Google Maps Hacks』。既に開発スキルを持つ人向けの書籍ではありますが、調べたおしてみようかと。そういう決断も、なか見!検索ではできませんしね。
| Google Maps Hacks 第2版 ―地図検索サービスをもっと活用するテクニック | |
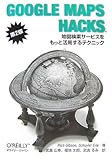 |
Rich Gibson Schuyler Erle 武舎 広幸 オライリー・ジャパン 2007-10-26 売り上げランキング : 562965 Amazonで詳しく見る by G-Tools |
円熟。円熟の歌手のアルバム、という表現がいちばんしっくり来ます。例えるなら由紀さおり?そんな感じ。
頑張らなくてもいいんだよなんて
今の僕には聞かせないで
(『Golden Road』/稲葉浩志)

ソロ3作目の『Peace Of Mind』がリリースされた時点で、「ソロはこれで終わりなんだろうな」と思ってました。なんとなく3作ってキリがいいし、『Peace Of Mind』というタイトルも象徴的だし、サウンド的にも素人の耳にも熟成していってるのが判ったし。ところが6年の時を挟んで『Hadou』がリリースされて、その破壊力に圧倒されて。『Hadou』はそれまでのソロ3作と違って、「稲葉浩志バンド」的な音で、歌詞もそれまで以上に稲葉スピリット全開で僕はソロ作品の中で最も好きです。アルバム構成も凄いし、ライブも凄かったし。『今宵キミト』の境地に呆然としたり、『絶対(的)』という(的)の使い方に驚愕したり。
なので、今年5作目のソロアルバムを出すと知った時、「あれ以上のもの出てくるのかなあ」と、これはB’zと違って少し不安な感情を持ってしまってて、どんなアルバムになるのか、稲葉浩志は必ず進化すると思って予想するとしたら、ソロ活動での「バンド」サウンドは一旦『Hadou』で行き着いたと思うから、より「ボーカリスト色」の強い曲で来るかなあ、と思っていたらアルバムタイトルが『Singing Bird』でひょっとしたら意図的にあってるのかな?と思いつつ、届いたアルバムを通して聴いてみたらこれは非常に円熟したボーカリストの、聴かせるためのシンプルでメロディアスな曲が詰め込まれたアルバムでした。音数もそんなに多くないと思いますし、絵で言うと水彩画のような?なんだったら2,3色しか使ってない水彩画のような。昔から聞いたことのあるような、奇を衒わない、歌声を聴かせるための曲。童謡のようかも。
なので、一聴するとあまりインパクトのない、さらっと聴いてしまうかもしれないアルバムですけど、ずーっと聴き続けたくなる大人のサウンド。そして今までの稲葉の歌詞が、アウフヘーベンを実践するような観念に満ちた歌詞だったけれど、それも「激情的」だったと思えるくらい、更に先に進んで円熟した精神性を示してくれる歌詞の数々。感涙。
例えば『Stay Free』:
自由ってどんなものでしょ
逃げるだけじゃこの手には掴めない
『孤独のススメ』なんかはまるごと引用したくなります:

そして、今の世間に逆行するかのような『Golden Road』に痺れます:
頑張らなくてもいいんだよなんて
今の僕には聞かせないで
ムリをしたっていいんじゃない
笑われたっていいんじゃない
誰かのものでもない
僕だけのゴールデンロード
しかしこのアルバムは、『photograh』にトドメを刺すと思います。いつもながらの稲葉得意のいたたまれない未練感の歌で、いい曲だなあ・・・と思いきや、ふと耳を突き刺すフレーズ:
人は誰もがいつか旅立つと
わかっているつもりでいたけれど
ああそっちなのか、この曲はそっちなのかと、B’zでも珍しい、『TINY DROPS』くらいしか例のない、そっちの曲なのかと、自分の年も思い浮かべながらしんみりと聴き入ったのでした。本当にいいアルバムです。
 |
Singing Bird 稲葉浩志 バーミリオンレコード 2014-05-20 by G-Tools |
「山へ行くつもりじゃなかった」はもちろん、『海へ行くつもりじゃなかった』のオマージュです。

先週末ひどい喉風邪をひいて体力以上に気力を失い、いい天気だったのに走りにも行かなかったしそれどころか何にもしない週末を過ごし、今週末こそはと思ってたら週半ばでぶり返して滅入ってしまったのですが、なんとか走れるかな、くらいまで体調を回復させることができたので、じゃあと駆り出したものの、どの程度走れるか自信がない。まだ鼻は通りきらないし、喉もぜーぜー言う。なので、とりあえず阪奈道路のてっぺんまで、阪奈を通るのは無理だったとき引き返せないから危険なので裏道で出てみて、上りきれたら大阪市内の平坦を走って遠出しよう、無理そうだったら引き返して富雄にかき氷でも食べに行こう、と思ってたのに、気がついたら何故か生駒山麓公園に向かう上りを駆け上がるはめに・・・
宝山寺登るより距離も短く楽そうなのに、実感は宝山寺より厳しいと思ったら、ルートログ見ると平均斜度は宝山寺より少し緩い8.5%くらいですが距離が1km長かったです。いい練習ルートかも。公園に辿り着いたあと、大阪側に出るにはダートを走るしか無いようで、それが嫌なら結局坂を下りきって出直しのようで、そんな気が起きるはずもなく、意気揚々と坂を下って『みやけ』へ。

好きなかき氷五本の指に入ります。店構えも魅力。ロードバイクと氷は絶対的にあいます。
途中でTRANSITの人にあったので、お願いしていたチューブを買いに立ち寄り。最近、立ち寄るとお客さんが続々と来るシーンしか見たことない。儲かってはります。TRANSITの人が出たついでにまたまた改めて独走会について、独走会と言うのは富雄の超絶カッコいい自転車屋TRANSITの走行会「おいしいポタリング」の参加者の(すごくカッコよく言うと)スピンアウトで、「独りで走る愉しさ」を知る大人の集団、ということにしています。独りで走ればそれでもう「独走会」。

正暦寺は奈良市の南東、山間部にあります。北から169号線を帯解寺あたりまで下ったら、正暦寺に登る道に入れます。
約3km・平均斜度3%、ほとんど車も人も通らず、気ままに登りを楽しめました。

孔雀明王という大変珍しい像にお目にかかれました。猛毒を持つコブラの天敵ということで健康の願いを叶えてくれるとともに、消し難い己の煩悩を断ち切ってくださいとお願いすることも修行僧にあったそうです。

住職さんが優しくて、車両進入禁止だけど今の時期は人もいないし門まで自転車持ってきて写真撮ってもいいよとおっしゃってくれたのですが、やっぱりそれは甘えすぎなと思って控えました。
それにしても体調がいまいちとは言え走れなかった。
50kmを過ぎて足が重くなり回せなくなり20km/hくらいしか出せず、富雄から阪奈沿いの登りも苦しかった。平地長距離走練習しないと。
去年も、シーズン初の炎天下はバテバテだった気もする。初独走会の長谷寺。
まだ元気があったときも、ケイデンスあげるとおしりがポンポン跳ねてたので、ちゃんと回せてないと思う、回す練習を心がけよう。
帰りは久しぶりにノモケマナ。ハード系がおいしいお店ですが糖分摂取にあんぱんを。ノモケマナのあんぱんは「たい焼きか!」ってくらい餡が入ってます。例によって撮る前に食う体たらく…この食い意地は治りそうにありません。
 |
three cheers for our side~海へ行くつもりじゃなかった フリッパーズ・ギター ポリスター 2010-01-27 by G-Tools |
独走会と言っても、別に「走るのは独りであるべし」とか言うわけでは全然ないのです。

またまた改めて独走会について、独走会と言うのは富雄の超絶カッコいい自転車屋TRANSITの走行会「おいしいポタリング」の参加者の(すごくカッコよく言うと)スピンアウトで、「独りで走る愉しさ」を知る大人の集団、ということにしています。独りで走ればそれでもう「独走会」。
ですが最初に書いたように「走るのは独りであるべし」と頑なな訳では全然ありませんで、どちらかと言うと必要に迫られたところのほうが大きいのです。割と忙しい業界に勤めるサラリーマンで、なおかつ勤務先は社員数がそんなにいなくて同じ趣味を持っている人がいないし、住んでいるところは生まれたところでも育ったところでもないので昔からの友人というのもいない訳で、必然的に独りで走る機会が増える訳です。
でも自転車というのは「独り」で愉しむことができるスポーツだし、パンクとか体力切れとかいろんなトラブルに遭遇しても自力でなんとかできてこそ愉しめるスポーツというところが、自立心を大切にする私の気風に妙にマッチして、TRANSITで知り合ったお友達の方々と走るのを愉しむ傍ら、「独り」で走るということも積極的に愉しもう、できればこの「独り」で走るということを、他の人とも共有したい、という、相反することをうまく融合したいという思いを形にしたのが「独走会」なのでした。

そんなTRANSIT一派の聖地・くろんど池。実は私はまともに行ったことがなくて今回初めてきちんと走りました。あれ、東側から来たら相当上りますね。今度、あの上りにもトライしてみようかな。

その下りを下りきった後、精華町に出てこの先どうしようかな~と考えた結果、県道52号を下って秋篠に出ることに。目的地はもちろん秋篠寺。

この苔だけを鑑賞に来られた方もいらっしゃいました。この日は日差しが抜群の明るさで、枝の影とのコントラストに見入りました。御朱印は年に一度しか貰えないそうです(ネットで調べると二回と書かれているサイトもありました)。

そしてこれもまた初めて、富雄の名店、boulangerie ASHに。店構えも可愛らしいので入ってみたくなる雰囲気満点なんですが、ドアをオープンした途端に目に飛び込んでくるパン達がどれもこれもすっごい綺麗。なんというか整っている、端正な、丁寧な綺麗さ。ガラス細工みたいでした、どれも。一気に「あれも欲しいこれも欲しい」モードになりましたがなんとか自分を落ち着けて厳選して4つ買いました。

が、写真撮る前に食べてしまう食い意地は健在で、なんとか間に合ったのがこのカレーフランス。ここしばらくハード系のパンをずっと買ってたんですが、久し振りにソフト系でおいしいと思うパンでした。ふんわりでさっと食べられておいしい。ハード系とソフト系、どちらのほうがおいしさ出すのが難しいんだろうなあと考えてみたりしました。
リハビリは順調。もう2,3本宝山寺こなせたら、いよいよ暗峠かな~。

前回は生駒総合公園への上りというなんとも弱気なコースでお茶を濁しましたので、少しまとまった時間の取れたこの日はいよいよ宝山寺までの上りを試すことにしました。家を出たときはあまりその気はなく、法隆寺まで行って帰ってくるド平坦コースをペース走、と思ってたのですが家を出て、あまりに爽快に晴れた陽の光の元緑眩しい生駒山を目の当たりにすると、アップもしないままするすると上りの入り口に向かってしまっていたのでした。

結果、14分くらい掛けてですが無事上りきれたので上々の復活具合と満足。あと2,3本、ペースを上げつつ練習して、暗峠に挑みたいなと思います。
そのまま降らず、南に進む道を流した後、第二阪奈を望むあたりで東進して下ったのですが、平均傾斜15度の坂を下るのは怖いです!下りなのに平地より全然スピード出てません。
"裏"東大寺は連休中でもこんなに落ち着いた佇まいです。
改めて独走会について、独走会と言うのは富雄の超絶カッコいい自転車屋TRANSITの走行会「おいしいポタリング」の参加者の(すごくカッコよく言うと)スピンアウトで、「独りで走る愉しさ」を知る大人の集団、ということにしています。独りで走ればそれでもう「独走会」。
GW連休最終日、少し走る時間が取れたので、思い立って東大寺戒壇院へ。戒壇院は「独走会」を思いついた記念の場所です。戒壇院は「戒を受ける」施設、つまり出家者が正規の僧になるために戒律を授けられる施設。それは制度によって認められるという言い方もできるけれど、「独り立ちする」ということでもある。そして戒壇院で戒律を授けるため唐から招かれたのは鑑真、5回の渡航失敗にも屈せず渡航を成し遂げた鋼の精神。その6度目の航海で嵐に飲まれた際、鑑真の船を救うべく船に現れたのが戒壇院に祀られる四天王。去年戒壇院を訪れた際、戒壇院に纏わるこれらの伝承を知って、これは私が自転車に惹かれる核心にかなり近いものがあると感じました。
時を同じくして、スッタニパータの「犀の角のようにただ独り歩め」という言葉を知ります。もちろんこれは孤立せよということを言っているのではなくて、かなりの程度修行が進んだ僧に対する言葉なのですが、ロードバイクでツーリングするのは、道中何があっても自分の責任、誰のせいにもせず言い訳もせず自分の選んだ道を走っていく愉しみというのは、この「犀の角のようにただ独り歩め」という境地に近づけるものなのではないか、そう閃いたとき、「独走会」の骨格が固まったのでした。

戒壇院北側の門です。少し段を登ります。



「戒壇院」の文字がシブい。当たり前なんですけどあらゆる品に、お堂の名前とかお寺の名前とか描かれてるんですよね、寺院って。ちょっとユーモラスでさえあります。

御朱印。四天王って言葉は誰でも知ってると思いますが、その像はあまり見ようとしたことがないのではないでしょうか。戒壇院でお会いされることをオススメします。

戒壇院の北すぐにあるカフェ「工場跡事務室」。昭和50年代半ばまで乳酸菌飲料の研究及び製造が行われていた建物、なので工場跡なんですね。木造の味が存分に活かされたレトロな喫茶で、コーヒーもトーストもすべて美味しいオススメの場所です。このエントリが"裏"東大寺の堪能のきっかけになれば幸いです。
何気なく、撮れていたムービーを見てみたら夕闇が存外に綺麗だったので。
暗くなるまでに少し時間があったので、前から気になっていた近所の神社まで行ってみました。住吉神社という名前で、脇には「おまつの宮」と彫られた石碑が建っています。

これは、交野の磐船神社から松の苗を移したことからそう呼ばれているそうです。磐船神社は饒速日命が降臨した神社なので、その神社の松の苗を貰ったというのは大きな意味のあることということなんでしょうね。近くのバス停も「お松の宮前」で、通称として通ってるんだと初めて知りました。

この写真とても気に入ってます。今まで自転車と撮った写真で1,2を争う好きさ具合です。建造物に立てかけずに撮ったところがいちばん気に入ってます。
近くの神社でも行ったことのないところがたくさんあるので、近場乗りでもまだまだ楽しめます。たぶん神社があるんじゃないかなという小さな森とか、機会を見つけては細かく行ってみよう。
期待以上の施設かも。生駒駅前図書室 木田文庫。

生駒駅前再開発で、「ベルテラスいこま」というちょっと大げさな名前の施設が建設されたのですが、私にとっての目玉は「生駒駅前図書室」。生駒ご在住の木田さんが一億円以上の寄付をなさったことから「木田文庫」という別名が与えられた生駒駅前図書室は、思ってた以上に使えそうな場所でした。家から一分でいけるし、ヘビーユーザーになるかも。

事前の案内で「読書カフェ」というのができることは知ってたのですが、正直に言うと、この自販機が置いてある閲覧コーナーがあって、屋外部分もある、というそれだけのことなんですが…

今日がオープニングなので結構な人がいるかな、と思いながら足を運んだのですが、多少時間が遅かった(16時頃)とは言え、少なくはないものの、閲覧コーナーが座ってる人でいっぱい、というほどのこともなく、比較的快適に使えました。
「図書館」ではなくて「図書室」と謳っているように、それほど本は置いてなくて、旧たけまるホールの図書室のように、子供向けの本で占められているんだろうと思っていたのですが、確かに絵本コーナー等広かったですが一般書も雑誌も意外と豊富でした。とは言えやはり「室」クラスの規模ですし、閲覧室も読書カフェも座席数は2,30席くらいの規模ではないかなと思います。こじんまりしたものです。
「こういうの、大阪とかだとどれだけキャパを見合うものつくっても人が溢れて不便なんだろうなあ」と思った時、こじんまりした規模で、まずまずの人が集まっているというこの生駒駅前図書室の状況が非常に好もしいものに思えました。このくらいの規模の都市なら、需要がスパイクしてもその影響はある程度の範囲で済みますが、大都市になるとスパイクは人気モールサイトのトラフィックのスパイクと同じでもはや桁が違いすぎて有効な手が打てず(それに対して手を打つと、平常時との差がありすぎてコストが掛かり過ぎることになる)、不便を強いるような状況になってしまいます。
自分の住む街が程よいサイズで自分の価値観というか趣向というかそういうのに近くて住み良いというのはとても幸せなことだなと思いました。そしてこの「サイズ感」というのはこれから大事にしていかなければならないことに違いないなと感じました。
本屋好きの私は客先から客先への移動中とか、少しスキマ時間があって通りがかりに本屋があると5分でも立ち寄ってしまうんですが、そんなとき「30秒立ち読み」というのをやっていて、ふと「これって実はオススメできるかも」と思ったので書いてみます。
「30秒立ち読み」というのは、今、巷に唸るくらい毎日毎日発刊されるビジネス系新刊、いわゆる「ノウハウ本」「ハウツー本」(”なんとかコンサルティングが1年目から叩き込むロジカルシンキング作法”とかそういうの)の、適当に開いたその節だけを読む、という立ち読みです。ただそれだけのことです。
今、ほんとに目も眩むくらいの数のビジネス書が「どこが出版不況なんだ!?」というくらいに発売されますし、そのタイトルは非常に扇情的で読んでみたくなりますが時間も足りないしお金も足りないし読んだところで行動しなければ意味がないとなんとなく薄々わかってる。でも、あの手のビジネス書に書いてあるのは、だいたい「頑張りましょう、さすれば報われます」くらいのことなんです、どんなにタイトルが扇情的でも。だとしたら、自分に行動を変えるためのきっかけになるような読み方をするのが、これらの本を読む上でいちばん重要なことであろうと思います。
そこで、どの一節でもいいですから、適当に開いたページを含む節だけを読みます。だいたいあの手の本はそういう意味ではうまく出来ていて、読ませやすいように節がすごく短くまとめてあります。だから逆にひとまとまりの節なら30秒くらいで読めてしまうのです。
そしてそれ以上は読まないことで、結構頭の中には鮮烈にその印象が残ります。自分でよく考えて、その知識を自分の血にまで持っていくかほどほどにしておくかは自分次第。でも、単に漫然と一冊最初から最後まで読む読書とはかなり変わってくると思います。
立ち読みを推奨するようなこと書いてもいいのか?というと、それに文句言ってくるのは著作権協会だけな気がしますが、自信を持って言えるのは、熱心に立ち読みする人のほうが本を買うということです。著作権協会は「すべての本を袋とじにして売りだしたらい」と去年くらいに言ってましたが、そんなことしたらそれこそ誰も買わなくなって出版不況だと思います。中身の確認ができない→表紙で扇情しようとする→そのうち、表紙が言ってることなんていい加減だという共通認識が生まれる→本が売れなくなる。絶対このスパイラルと思う。ちなみに私は昨年だけで多分5万は下ってないと思います、本屋で本買った金額。